
赤ちゃんの夜泣きが続く中、「どうして旦那は起きないの?」「一人で全部やるのがつらい…」と感じたことはありませんか?特に共働き家庭では、どちらも疲れているはずなのに夜間の育児が一方に偏ってしまうことがよくあります。この記事では「夜泣きで旦那が起きない」問題について、実際の声や原因、そして現実的な解決策を紹介します。
目次
夜泣き中に起きない旦那…その態度にイライラする理由

夜泣きに対応しているのに、隣で何もせず眠っている旦那の姿を見ると、不満が募るのは自然なことです。妻の負担ばかりが大きくなることで、夫婦の関係にひずみが生じてしまうケースもあります。
夜泣き対応は妻だけ?「旦那がむかつく」と感じる瞬間
夜泣きが続く日々の中で、「なんで自分ばかり…」という思いに駆られる瞬間は誰にでもあります。旦那が全く起きずに眠り続ける姿を見ると、むかつく気持ちが湧いてくるのは自然なこと。特に日中の育児や家事でも負担が多い場合、その不公平感は一層強くなります。
「手伝わない旦那」に限界…家庭内ギャップの正体とは?
「手伝う」という言葉の裏にある「育児は妻の仕事」という暗黙の前提。これがある限り、夫婦の役割分担は平等にはなりません。夜泣き対応も同様で、旦那が自分の役割として認識していない場合、手伝う意識すら芽生えにくくなります。このギャップこそが、多くの夫婦のすれ違いの根本原因です。
「聞こえない」は言い訳?夜泣きに無反応な男性の脳の違い
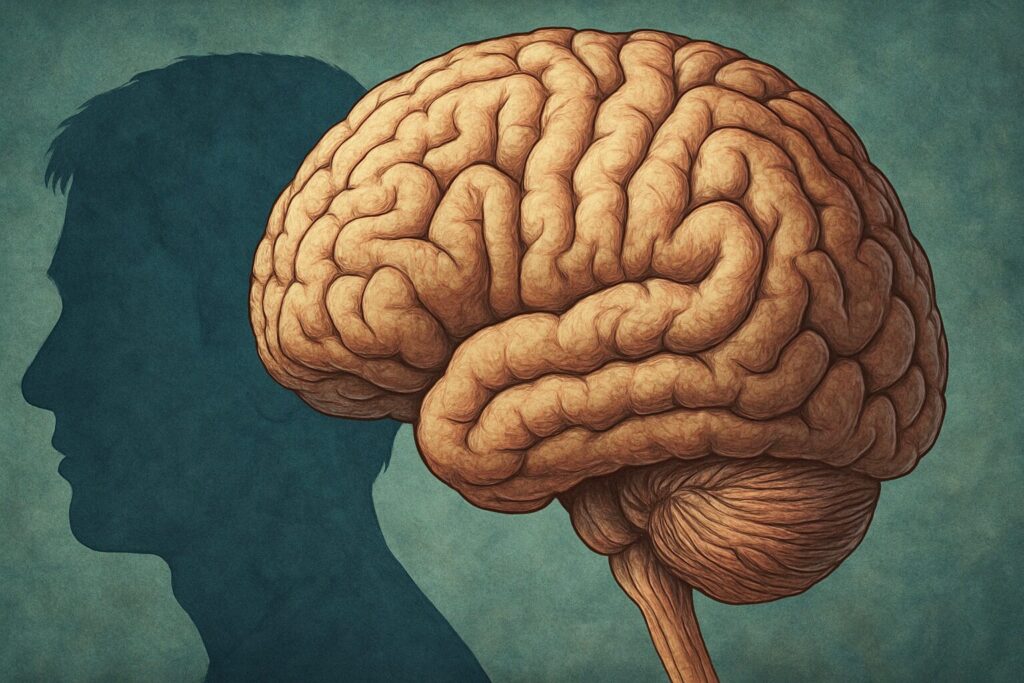
「起きたくない」のではなく「本当に聞こえていない」可能性があるのをご存知ですか?脳の働きの違いやホルモンの影響によって、男性は赤ちゃんの泣き声に気づきにくい傾向があります。
「男には聞こえない」は本当?脳科学的な違いを解説
実際に、男性と女性とでは脳の働き方に違いがあります。女性はホルモンの関係で赤ちゃんの泣き声に対して敏感に反応する一方、男性は深い睡眠に入りやすく、泣き声を感知しにくい傾向があると言われています。つまり、起きないのは“意識の低さ”だけではなく、ある種の生理的な理由も存在するのです。
夜泣きに気づかない旦那へのアプローチ方法と伝え方の工夫
「何度言っても起きない」と感じたら、言い方を見直してみましょう。怒りをぶつけるよりも、冷静に「どうして欲しいのか」を伝える方が効果的です。夜の育児の記録を共有したり、具体的な行動をお願いしたりすることで、旦那自身の当事者意識が芽生えるきっかけになります。
共働きなのに私だけ?夜泣き対応の不公平感をなくすには
共働き家庭では、お互いに疲れているはずなのに夜の育児だけが妻に偏る…という状況が続くと、不満やストレスが積もりやすくなります。公平な分担を実現するには工夫と話し合いが欠かせません。
「共働きだからこそ分担を」疲労のバランスを話し合う方法
共働きであれば、育児も「お互いにできる範囲で協力する」姿勢が欠かせません。「自分も仕事があるのに…」という不満は、相手に伝えなければ伝わりません。夜泣き対応を“当番制”にする、翌朝の支度を分担するなど、現実的な方法で役割分担を可視化することが鍵です。
「仕事があるから仕方ない」は正当化?話し合いのコツと代替案
仕事を理由に夜泣き対応を拒否されると、「私の仕事は軽視されているの?」という不満が生まれます。そんなときは責めるのではなく、協力できる時間帯や方法を一緒に考えることが大切です。早朝対応や休日夜の交代など、無理のない代替案を提案してみましょう。
解決策としての“別室”はアリ?夫婦関係を壊さないために

寝不足によるストレスがピークに達する前に、物理的な距離を取ることでお互いに心のゆとりを持てることもあります。「別室」という選択肢には、実は前向きな意味もあるのです。
「別室」で眠れるのは誰?夫婦のバランスを取るルール作り
夜泣きによる寝不足が蓄積すると、どちらにとっても健康的ではありません。別室での就寝を導入する場合、夫婦のどちらがいつ休むか、どのようにフォローし合うかを事前に話し合っておくと安心です。交代制や曜日ごとの当番制など、明確なルールがあれば、トラブルの回避にもつながります。
「一人じゃない」と思える夜泣き対応の体制づくりとは?
夜泣きに直接対応できない場合でも、声かけや感謝の気持ちを伝えることで妻の心の負担は大きく変わります。「ありがとう」「今日もお疲れさま」といった一言があるだけで、「自分だけが頑張っているわけじゃない」と感じられるようになります。育児における“心の分担”も大切なのです。
夜泣き対応は大変な育児の一部ですが、「一人じゃない」と思えるだけで気持ちは大きく変わります。夫婦でよく話し合い、役割を調整しながら、無理のない体制を作っていきましょう。
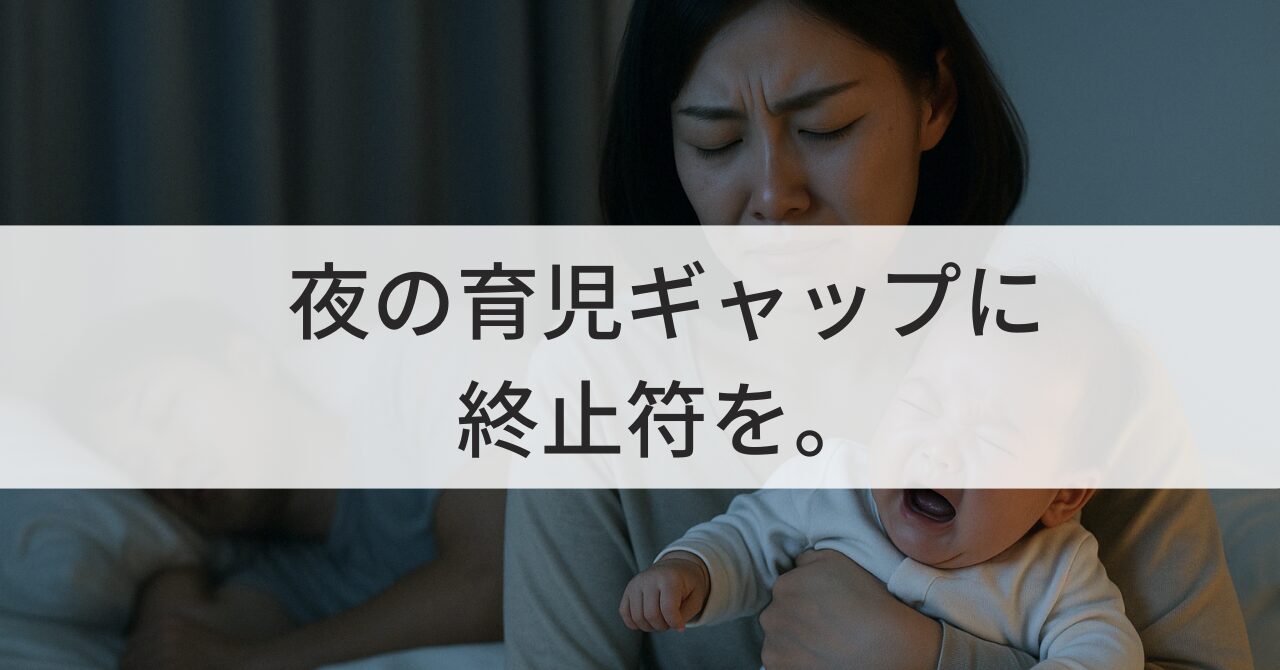

コメント